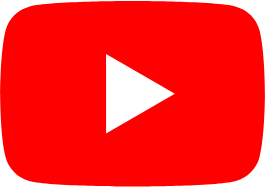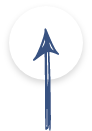近年、小児特に低年齢児の虫歯(むし歯)の成因については様々なことがわかってきていますが研究は途上にあり、
ますます混沌としてきています。
WHOの「砂糖と虫歯」というレポートで虫歯(むし歯)は非感染性疾患(noncommunicable disease)と表現されていて、
従来言われていたようなミュータンス菌を主原因とする感染症とはニュアンスが異なってきました。
生態学的プラーク仮説と言って、口の中の様々な細菌が関わり合う歯の表面の歯垢の中の環境の変化が、
その状況によっては虫歯(むし歯)を発症させるという解釈が台頭しています。
また、早期小児う蝕(低年齢で重度の虫歯(むし歯)になるケース)にはスカルドビア菌やビフィドバクテリウムといった細菌の関与がわかりつつあります。
カンジダアルビカンスという真菌の仲間とミュータンス菌が協働して低年齢児の重度虫歯(むし歯)の成り立ちに関わっていることも研究されています。
このカンジダアルビカンスやミュータンス菌は保護者由来の場合が多いので、1999年当時に書いた下の文章もまちがいではないとは言えます。
しかし、唾液を介して成人から乳児に伝播したミュータンス菌が単独で虫歯(むし歯)を直接発症させるというわかりやすいストーリーではなさそうです。
上記した中には、保護者の責任に帰することのできない虫歯(むし歯)の発症メカニズムも含まれています。
低年齢で重度の虫歯(むし歯)になったお子さんの中には、たしかに生活の中の食品や飲料に問題があるケースもみられる一方、
極端な食生活や習慣がないという場合もあり、保護者はご自分を責めてしまうのに原因がわからなくて混乱します。
さらなる研究成果が出てくるのを待つしかありません。今後、0歳から虫歯(むし歯)予防に大きく寄与しそうな要素は、
フッ化物配合歯みがき剤を年齢に応じた濃度と量で使用すること、CMに惑わされずに低年齢児の歯に良くない飲み物を避けることなどでしょう。

ここから下の文章は1999年当時の知見に基づいて書いたものですので、
上記した最近の研究結果と矛盾する部分があります。
また、授乳や哺乳瓶の使用の完了時期も1歳6か月頃とされるようになりましたので下記の内容には古い部分もあります。
しかし、低年齢児の重度虫歯(むし歯)の治療に日々取り組んでいる身としては、
虫歯(むし歯)で苦しむお子さんがひとりでも減ることを願っており、
知識や情報をアップデートしつつも過去の取り組みを反映する下の文章もそのまま残すことにしました。
■0歳からの虫歯(むし歯)予防
■出産の前にできること
虫歯(むし歯)の主な原因菌は「ミュータンス菌」と呼ばれる細菌です。虫歯(むし歯)はこの菌を中心として起こる「感染症」です。
その成り立ちは少し複雑ですが、つまりはかぜやはしかと同じく微生物を原因とした「うつる病気」です。そしてミュータンス菌は
「歯」がないと定着したり増えたりできない性質を持っています。
生まれたばかりの赤ちゃんは口の中にミュータンス菌を持っていません。5歳児のほとんどがこの菌を口の中に持っています。ミュータンス菌はどこからやって来るのでしょう?
実は、子育てをしている人(多くの場合はお母さん)の口の中から唾液を介して感染するのです。
しかし、ミュータンス菌が存在しても、すぐに虫歯(むし歯)ができるわけではありません。 また、
この親から子への感染を完全に防ぐことは残念ながらできません。
ある程度以上の数のミュータンス菌が入ってきて定着し、
さらに増殖していくと虫歯(むし歯)になる危険が増していきます。ミュータンス菌にとって好都合な環境、すなわち歯がはえて、
砂糖が頻繁に入ってきたりジュースなどで口の中がいつも酸性になっていたり、
ブラッシングで菌を取り除くことをしなかったりするとさらに危険は増していくわけです。
妊娠や出産の前に、これから生まれて来る赤ちゃんのためにできることは、お母さんの口の中のミュータンス菌の数をできるだけ減らし、
活性を低くしておくこと、つまり、お母さんに虫歯(むし歯)があれば完全に治療し、歯をよくみがいて清潔な口の中にしておくことが、
赤ちゃんへうつる菌の数や強さを最小限に抑えることにつながります。
■1歳頃までにすべきこと
デンマークのある地区では、赤ちゃんが生後9か月になると、赤ちゃんとお母さんは保健センターに呼ばれます。
そこでは、ライト付きのマウスミラーと、家庭で歯の状態を記録するための「歯科検診手帳」を渡されます。
そして、お母さんは、赤ちゃんの口の中の観察のしかた、記録のつけ方を習い、定期的に通ってチェックを受けます。
このシステムの中で、お母さんたちは赤ちゃんの口を観察し、生えてきた歯に触れることに慣れ、やがてブラッシングも上手にできるようになります。
この、「口の中をみたり触ったりすることに慣れる。」ことが、虫歯(むし歯)予防の第一歩としてとても大切なのですが、
日本のお母さん、お父さんがちょっと苦手な部分かもしれません。
口だけでなく、鼻、耳、肛門などの見えにくい部分の毎日の観察は健康チェックの上で役立ちます。虫歯(むし歯)を予防するために1歳頃までにすべきことは2つあります。
その1つ目は
①毎日、口の中を観察し、歯に触れることです。
歯が生えてきたらマウスミラーをつかって観察しましょう。
4本ほどそろったら小さな歯ブラシでみがきはじめてみましょう。
さて、この頃までにすべきことの2つ目はなんでしょうか?
それは満1歳頃までに
②母乳、ほ乳びんを卒業することです。
1歳から1歳6か月頃に虫歯(むし歯)ができてしまう場合、ほとんどが母乳またはほ乳びんによる授乳方法に原因が求められ、
非常に重度の虫歯(むし歯)も稀ではありません。
逆に考えれば1歳頃までに母乳、ほ乳びんを卒業できれば、普通の生活をしている限り2歳前に虫歯(むし歯)ができることは少ないのです。
育児にはいろいろな考え方がありますし、早い離乳をすすめない人もいます。
また、母乳やほ乳びんを続けていても虫歯(むし歯)にならない子もいます。
しかし、長い時間母乳やほ乳びんを吸っている場合や、子育てしている人(多くの場合はお母さん)の口の中に虫歯(むし歯)が多い
(今は治療済みでもかつては多かった場合も含みます。)ときは要注意です。
母乳、哺乳びんによる重度の虫歯(むし歯)ができる場合には
次のようなパターンがあります。
・母乳がなかなかやめられず、1歳をかなり過ぎてしまった。寝かしつける時に授乳するのが習慣となってしまい吸いながら眠ってしまう。
・ほ乳びんも母乳同様1歳を過ぎても卒業できず、手に持たせて与えっぱなしにしている。ほ乳びんの中身は人工乳、
フォローアップミルクでも虫歯(むし歯)になるが、果汁、乳酸飲料等ではさらに重度の虫歯(むし歯)となりやすい。
・下痢などのときに脱水予防として「スポーツドリンク」を与え、ほ乳びんで飲ませることが習慣化してしまった。
あなたのお子さんはこうした習慣がついてしまっていませんか?
■虫歯(むし歯)は生活習慣病でしょうか?
さて、従来から言われている虫歯(むし歯)予防法に、「歯をよくみがく」「甘い物は控える」というのがあります。
確かに毎日の歯みがき習慣がしっかりできていて砂糖を多く含んだ食品を少ししか食べない人は虫歯(むし歯)になりにくいと言えるでしょう。
でも、(0歳からの虫歯(むし歯)予防)でも触れましたが、基本的に虫歯(むし歯)は子育てをした人(多くの場合はお母さん)から乳幼児期に感染を受ける病気であり、その後の食習慣やブラッシング習慣の影響もあるとはいえ、かかりやすさが人によって違います。
たとえば、小学校4年生のAちゃんは気をつけているつもりなのにすぐに虫歯(むし歯)ができてしまいます。
同級生のBちゃんは甘い物が好きで、歯みがきも熱心でないのに虫歯(むし歯)がほとんどできない、という具合です。
虫歯(むし歯)が多くできてしまうAちゃんとあまりできないBちゃんは、そもそものスタートラインである虫歯(むし歯)の原因菌(ミュータンス菌)
の感染の状況が違うことが考えられます。
Aちゃんの場合は乳幼児期に感染を受けて以来、虫歯(むし歯)にかかりやすい口の中の状態が続いているわけで、
Bちゃんに比べて虫歯(むし歯)にかかるリスクが高いと言えます。
そして、これは本人の責任ではありませんし、日頃の努力が足りないからとも言い切れません。
虫歯(むし歯)は「歯のために良くない生活習慣」が原因であるという側面も確かにあるとはいえ、
同じような習慣を持っていてもかかりやすさが人によってかなり違うという特徴も合わせ持っています。
「甘い物ばかり食べるから虫歯(むし歯)になるんだよ。」とお子さんをしかるのはかわいそうな気がしませんか?