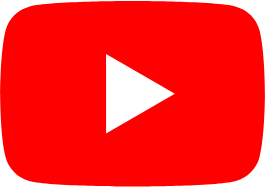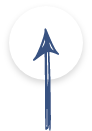2007年01月15日
小児歯科ってなに? その3
寒さも厳しい毎日ですが、我が家のまわりではスイセンがきれいに咲いています。枝から枝へ飛び交うメジロたちも元気いっぱいです。そして、私の診療所に定期診査に来てくださるお子さんたちも冬なのに元気です。
前回までは、小児歯科の仕事の内容について書きました。ところで町を歩いていると、歯科医院の看板はたくさんありますよね。そして、「小児歯科」と書いてある歯科医院も少なくありません。厚生労働省の資料(平成14年のものなので少し古いですが)によれば、全国の歯科診療所数は約6万5千軒ですが、そのうち「小児歯科」を標榜(ひょうぼう=看板に掲げること)しているのは3万軒弱です。つまり、半数近くの歯科医院には「小児歯科」と書いてあることになります。歯科医院を開業した場合に標榜できる科名は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つです。そしてこれらを標榜するのに資格や条件はありません。ですから、小児の患者さんを診療する意思がある歯科医師は「小児歯科」も標榜するのがむしろ普通です。
一方で、日本小児歯科学会の会員数は4千名ほどしかいません。そして、最近広告への記載が許可された小児歯科専門医と認定医の数は計2千名にも満たないのが現状です。学会に入会するだけなら会費さえ納入すれば良いのですが、残念ながら小児歯科を標榜している歯科医院の9割は日本小児歯科学会の会員ではありません。
祖父母から孫やひ孫までのご家族全員がひとりのかかりつけ歯科医に診てもらっているような場合もあるでしょうし、専門医でなくても学会員でなくても、小児や乳幼児の診療に長けている歯科医師は数多くいます。人口の少ない地域や離島には歯科に限らず専門医が少ないのはやむをえないかもしれません。
しかし、「標榜科」について、上記したような事情を理解していないと「小児歯科」と書いてある歯科医院を受診したのに「もう少し大きくなって泣かなくなってから来てください。」と言われてしまって困ったなどということが起きてしまいがちです。
受診する側のニーズと医療を供給する側の体制にずれがあると、希望した結果が得られないのは医科でも歯科でも同じなのです。
低年齢児の重度むし歯(虫歯)(1歳7か月)
上のケースの治療後